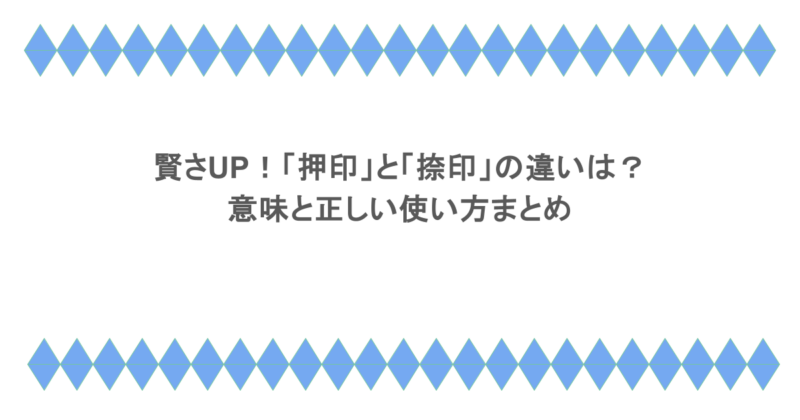ハンコを押すとき、「押印?」「捺印?」と迷った経験はありませんか?
契約書や役所の手続きなど、大事な書類を前にして「ご捺印ください」や「押印のこと」といった指示を見ると、どちらが正しいのか、何か違いがあるのか迷うこともありますよね。この記事では、そんな「押印」と「捺印」の違いや正しい使い方を分かりやすく解説していきます。
「押印」と「捺印」の違いは?
実は「押印」と「捺印」という言葉は、辞書の上でも法律の上でも「ハンコを押す行為」を指す、全く同じ意味の言葉です。では、なぜ二つの言葉が存在し、使い分けられているのでしょうか。それにはちゃんとした理由があります。
もともと、ハンコを押す行為は古くから「捺印」と呼ばれていました。しかし時代が進み、法律の条文などを国民にとってより分かりやすくするため、一般的に使われる漢字リストである「常用漢字」にない「捺」の字を避け、より簡単な「押」を使った「押印」という言葉が、新しい法律や公文書で使われるようになったのです。
つまり、言葉のルーツは「捺印」が先輩で「押印」が後輩という関係性ということです。
【本当の違いはココ!】「署名」と「記名」
言葉の意味は同じなのに、ビジネスの現場ではなぜ「押印」と「捺印」が使い分けられているのでしょうか。
それは、「署名(しょめい)」と「記名(きめい)」という二つの言葉に隠されています。この違いについて理解しておきましょう。
署名(しょめい)とは?
本人が自筆で名前を書くこと、いわゆる「サイン」のことです。
本人がペンを持って書いたという点が重要です。
記名(きめい)とは?
手書き以外の方法で名前が記されているもの全般を指します。
パソコンでの印字、ゴム印、他人による代筆などがこれにあたります。
捺印(なついん)とは?
「署名捺印(しょめいなついん)」の略で、本人が手書きした名前(署名)の横に、ハンコを押すことを指します。
押印(おういん)とは?
「記名押印(きめいおういん)」の略で、印刷やゴム印などで記された名前(記名)の横に、ハンコを押すことを指します。
この使い分けは法律で厳密に定められているわけではありませんが、実務上はこの認識が広く浸透しています。
「押印」と「捺印」の使い分け早わかり表
| 一般的な呼び方 | 正式な言い方 | 名前の書き方 | 法的な証拠力 | 主な使われ方 |
| 捺印 (なついん) | 署名捺印 | 本人の手書き(署名) | 強い | 重要な契約書 役所への届出など |
| 押印 (おういん) | 記名押印 | 手書き以外 (印刷、ゴム印など) | 弱い | 見積書 請求書 領収書 社内文書など |
【どっちが強い?】証拠能力のパワーランキング!
では、「署名捺印」と「記名押印」では、どちらが法的に「強い」のでしょうか。
これは、万が一トラブルが起きて裁判になった際、「その書類が本当に本人の意思で作られたものか」を証明する力、すなわち証拠能力の強さに関わってきます。
- 最強:署名捺印(手書きサイン + ハンコ)
- 強い:署名のみ(手書きサインのみ)
- 普通:記名押印(印刷された名前 + ハンコ)
- 効力なし:記名のみ(印刷された名前のみ)
「署名(手書きサイン)」が強い理由は筆跡にあります。
手書きの文字にはその人固有の癖が表れるため、争いになった際には筆跡鑑定(ひっせきかんてい)によって、本人が書いたものかどうかを証明できます。
二段の推定(にだんのすいてい)
法律の世界には「二段の推定(にだんのすいてい)」という考え方があります。
これは、記名押印の場合、
- 「その印影が本人のハンコのものであること」
- 「本人が自らの意思で押したこと」
という二つの段階を経て、初めて本人の意思だと推定される、というものです。
一方で署名は、筆跡鑑定だけで本人性を証明できるため、一段階で強い証拠能力が認められます。
【実践編】ビジネスでの正しい使い分け
理論がわかったところで、実際のビジネスでの使い分けを見ていきましょう。
基本は、その書類の重要度やリスクの大きさに応じて判断します。
ここぞという重要場面では「捺印(署名捺印)」
法的に重要度が高く、後々のトラブルを絶対に避けたい場面では、最も証拠能力が高い「署名捺印」を選びましょう。
例えば、
- 不動産の売買契約書
- 高額な融資契約書
- 企業の将来を左右する業務提携契約書
などがあります。金額が大きかったり、長期にわたって会社を拘束したりする契約には、強い証明方法を用いるようにしましょう。
日常的な業務では「押印(記名押印)」でOK
一方で、日常的に発生する比較的リスクの低い書類については、効率性を重視して「記名押印」で十分でしょう。
毎回手書きでサインするのは大変ですから、
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 社内稟議書(りんぎしょ)
などでは、記名押印が一般的です。
ちなみに、請求書や領収書への押印は法律上の義務ではなく、あくまで「会社が正式に発行した」という信頼性を示すためのビジネス慣習となっているようです。
【豆知識】なぜ日本はハンコ社会?世界との違いは?
日本のハンコ文化は古く、紀元前のメソポタミアにまで遡るようです。日本に伝わった当初は権力者の象徴でしたが、江戸時代には庶民にも広まり、日本のハンコ文化を決定づけたのが明治時代です。
1873年(明治6年)、公的な書類に実印を使うことが法律で定められ、国民皆が苗字を持つようになったことと相まって、現代に至る「ハンコ社会」の礎が築かれています。
世界との違いは?
一方で世界に目を向けると、欧米では手書きのサインが絶対的な基本です。重要な契約では、第三者である「公証人(Notary Public)」が本人の意思を確認し、サインを証明する制度が利用されています。
また、中国では個人のサインより会社の公式印鑑である「公章」が強力で、韓国では日本と同様に印鑑とサインが併用されるなど、契約における「信頼の証」の形は国や文化によって様々です。CRMマーケティンに関する韓国の記事を見つけました。韓国でも日本と同じようにビジネスに関する基礎的なことを学びたい人は多いのかもしれませんね
まとめ
「押印」と「捺印」の違いから世界の契約文化まで、ご紹介しました。
これらの知識は、単に間違いを避けるためだけのものではありません。自信を持って行動するための武器となります。押印や捺印の意味合いや使い方で迷った際には是非今回の内容を参考にしてみてくださいね!